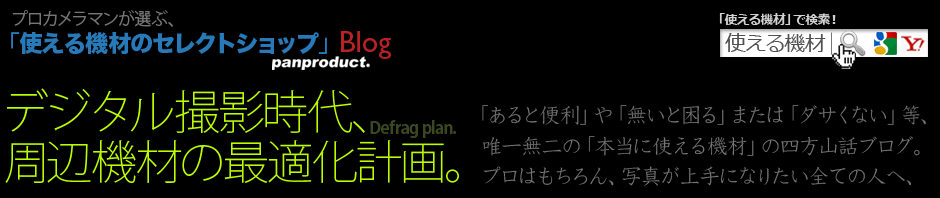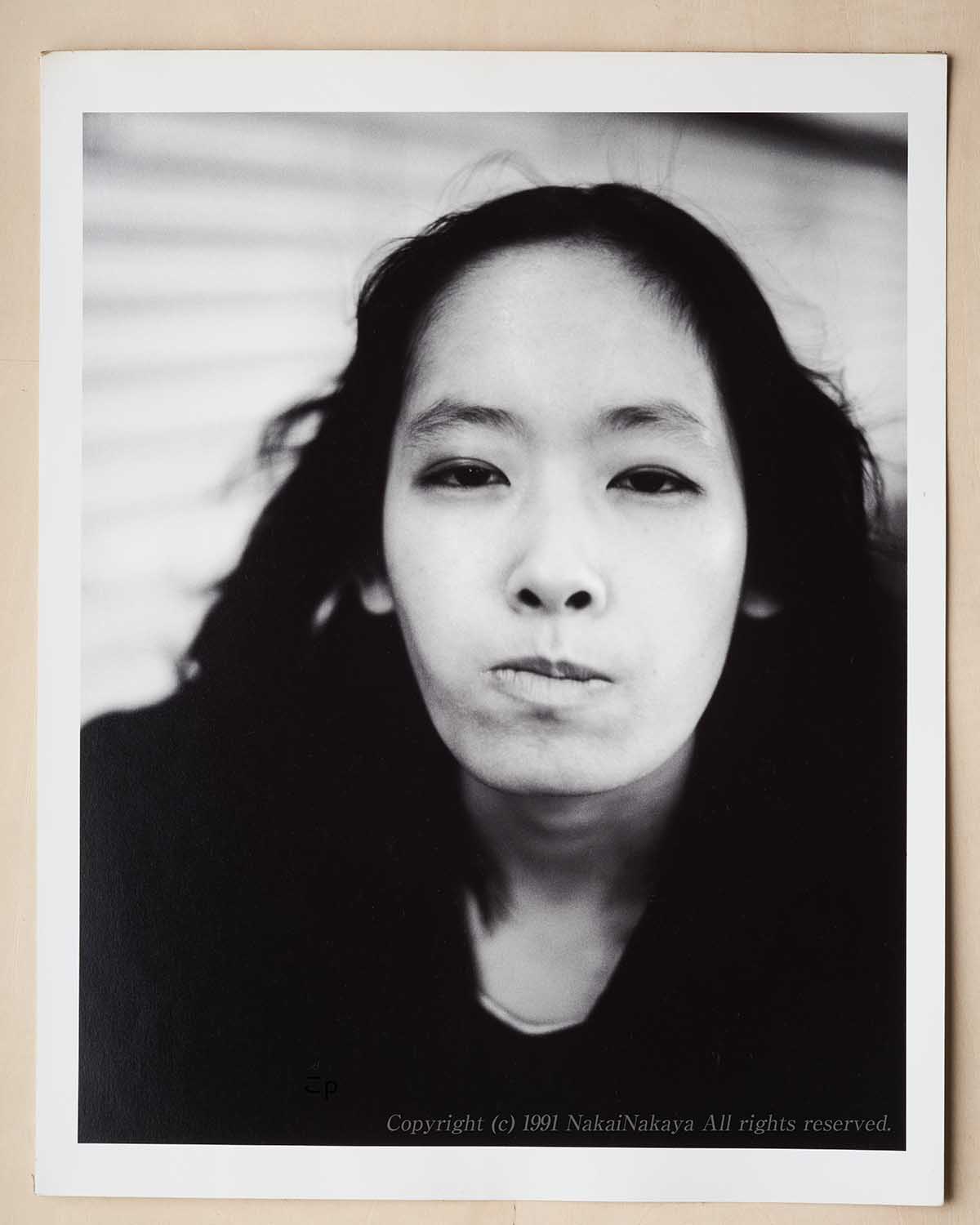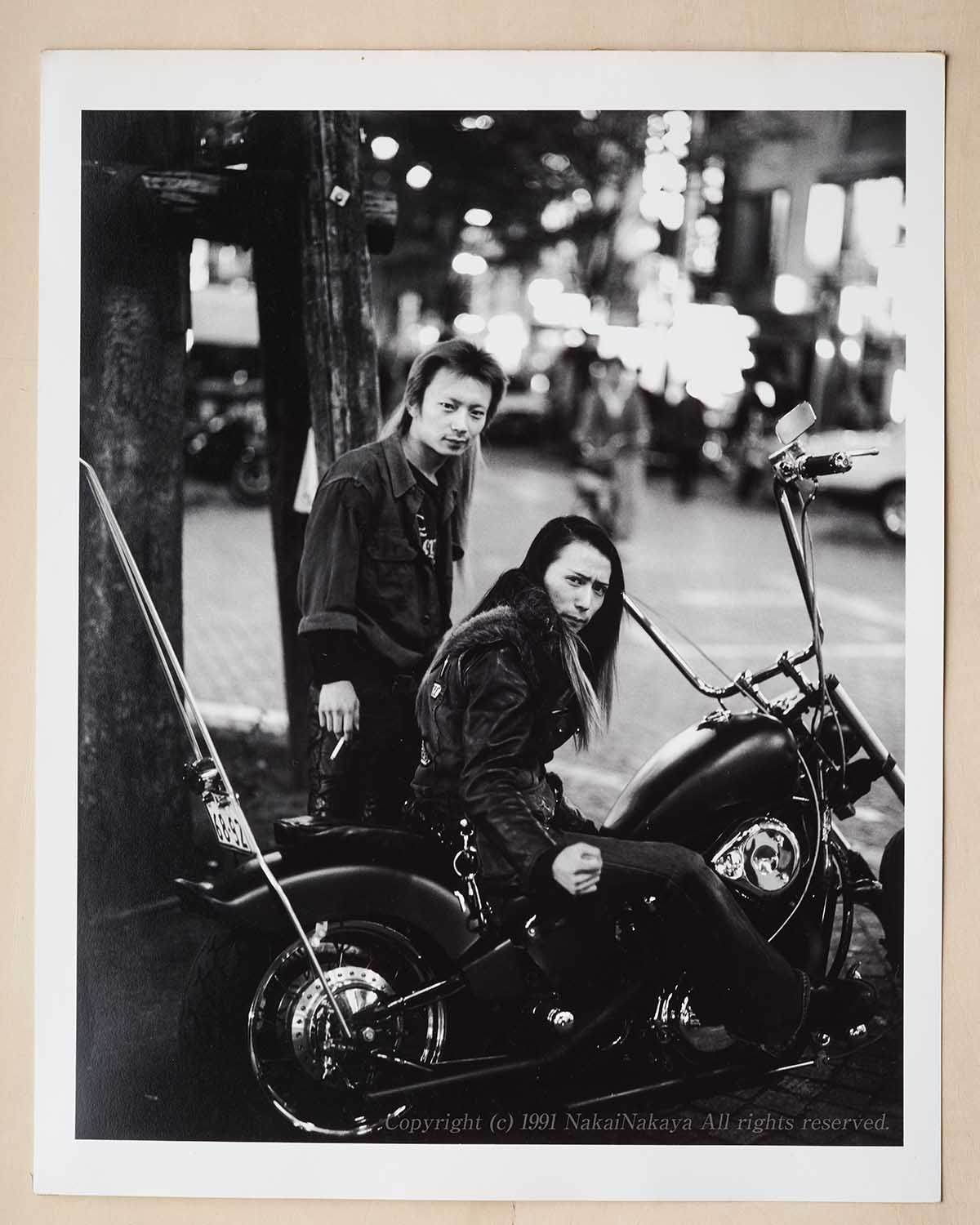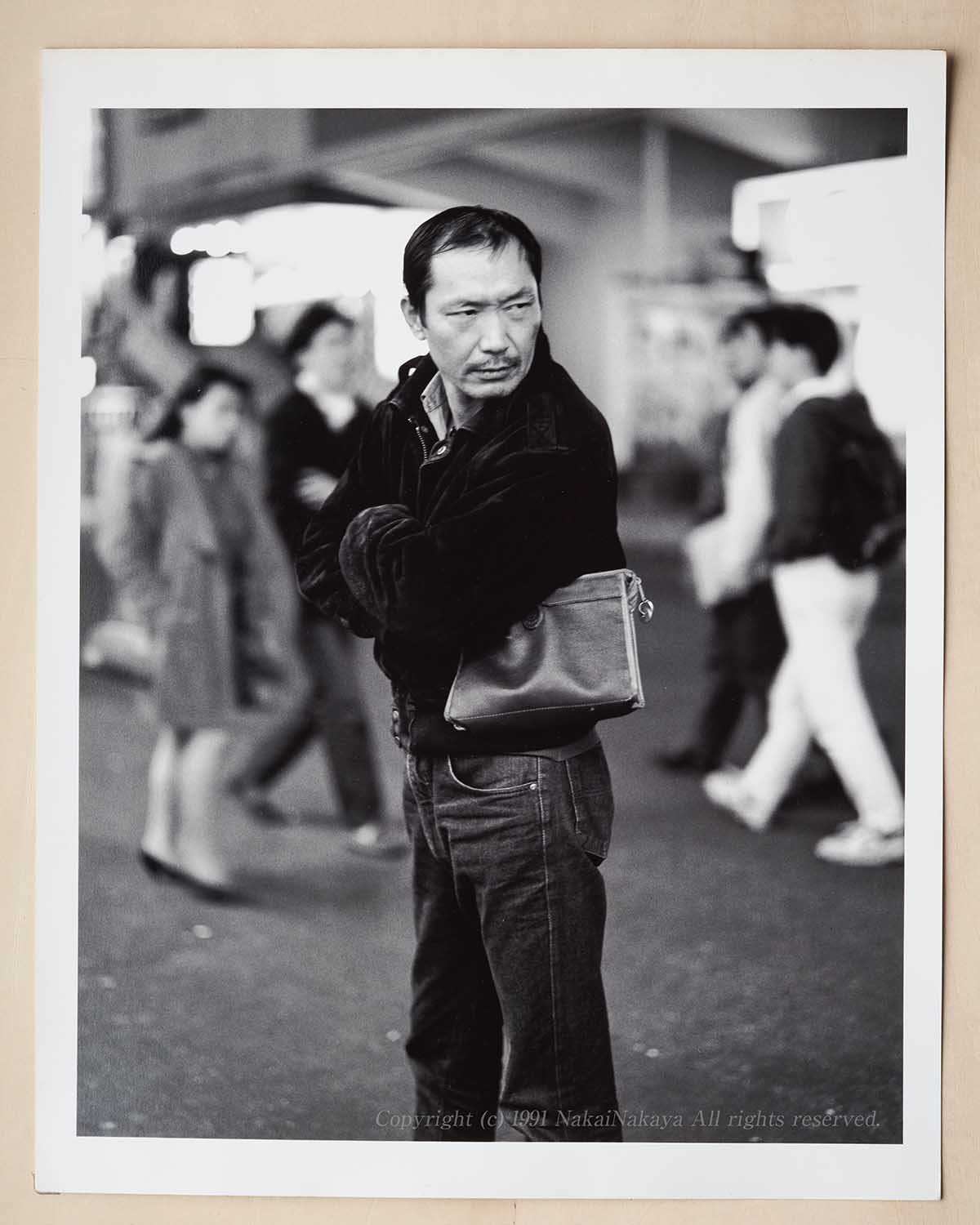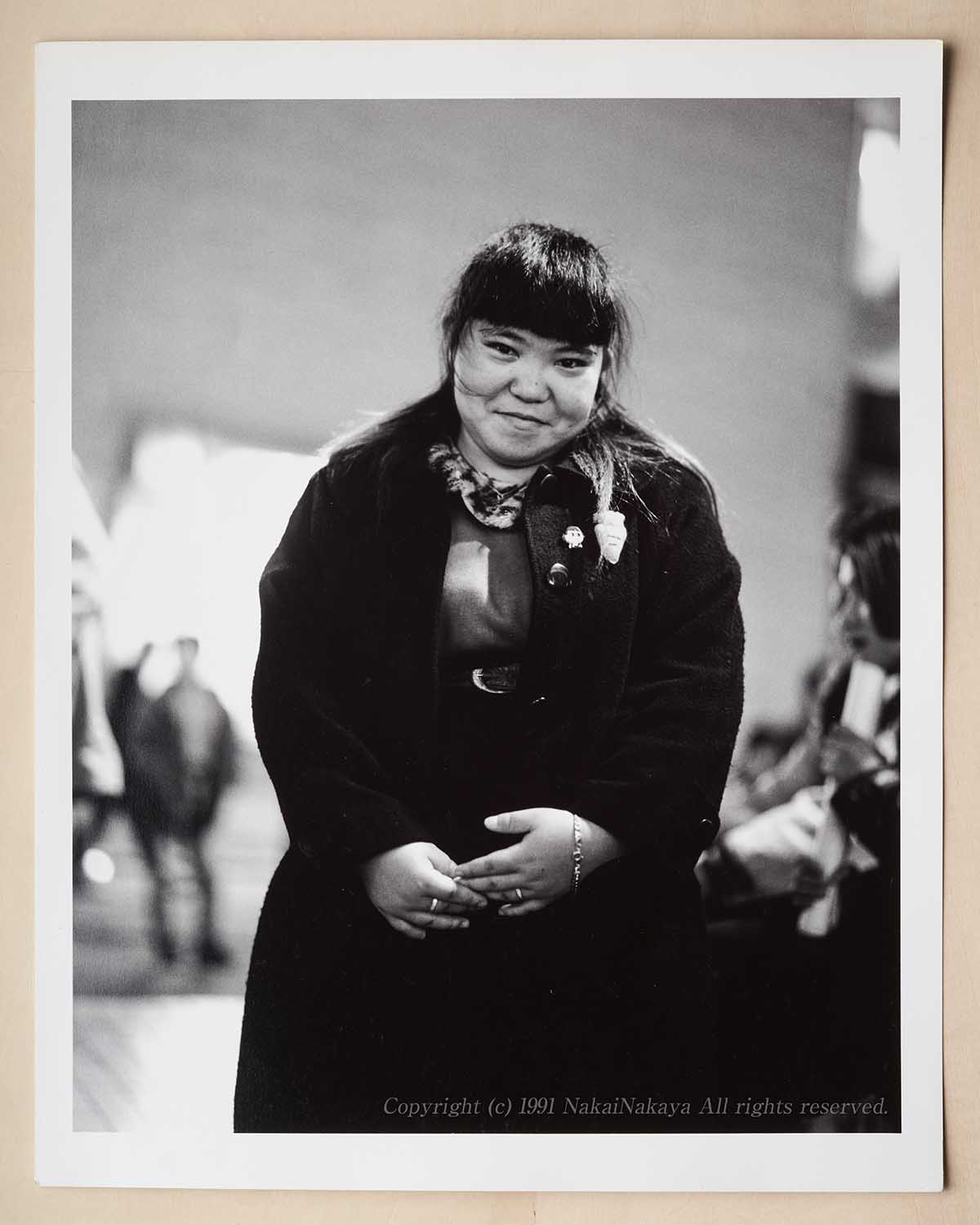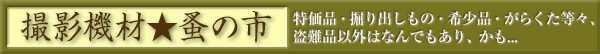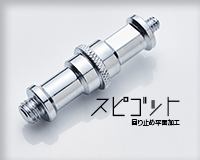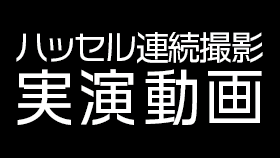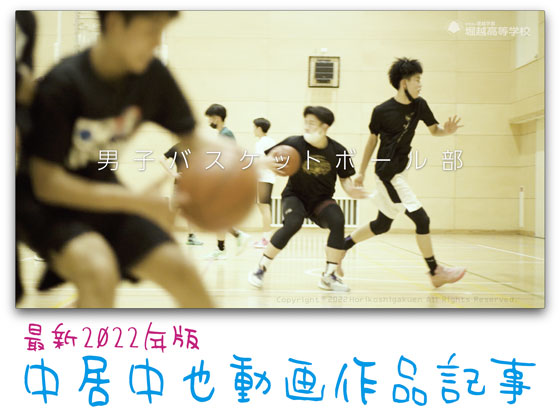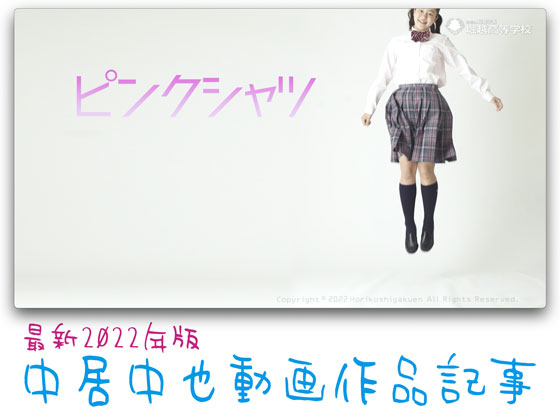ところが「真下振り」にしようとソケットの首の角度を下に向けると、ノブが当たってしまい真下に降ることができません。
このようなちょっとだけ残念なことが、撮影の照明機材では、まま良くあることです。
仮に、そのノブが「ねじノブ」の場合、この問題を解決できることがあります。その方法をこのE26ソケットを例に、ご説明させていただきます。
※逆に「ナットノブ」の場合は解決できないことが多いこのソケットは、ノブを外すと本体側にはナット(ねじ穴)がある構造になっています。
ここに、短めの「M6ボルト(M6ねじ)」をねじ込みます。M6のボルトは一般に流通する規格ものなので、ホームセンターで入手可能です。(ただ、長さは細かく選べないかも。絶対あるのは、M6-10、M6-20かな…)
たった、これだけのことで無事「真下振り」ができるようになりました!実は、撮影照明機材に使用されている「ねじノブ」の多くは、「M6ねじ」か「1/4インチねじ」のいずれかが使用されています。(稀に「M5ねじ」の場合もあり) これらの規格の短めのねじがあれば、代用できる可能性があるということです。
補足として「M6ねじ(6mm)」と「1/4インチねじ(6.35mm)」の簡易的な見分け方をお教えいたします。
定規で直径を目分で測ってみてください。6mmにわずかに満たないものは「M6ねじ」。6mmをわずかに超えているものは「1/4インチねじ」です。 この簡易手法で、おおよそ合ってるとおもいます。(M5は5mmにわずかに満たないねじ)
最後に追加情報。
ノブのねじ交換は「ノブが当たって角度が変えられない問題」の解決できるだけではありません。
普段「メスダボ先スタンド」をお使いの方の場合、スピゴットを照明機材にボルト
(ねじ)を工具で締め付けて完全固定して「オスダボ化」しておくと、いちいち悩まずに便利になるとおもいます。
というわけで、
「ノブ」の正体は、実は「規格ねじ」だった!ってことだけを覚えておくと、応用できる場面が必ずあるとおもいます。。
※特殊なノブを使っている機材はダメけどね..。
 E26ソケット (16mmメスダボ付)
E26ソケット (16mmメスダボ付)
 16mmダボ付 Cクランプ
16mmダボ付 Cクランプ
 回り止め平面加工・特注スピゴット(Φ16mm規格)
回り止め平面加工・特注スピゴット(Φ16mm規格)



↓ 緊急事態宣言発令中ということを考慮して配信を自粛ちぅ。(読者様の心理的ストレス軽減のため)
![]()